【紅葉の名所】近江屈指の古刹「湖東三山」の魅力を徹底ガイド
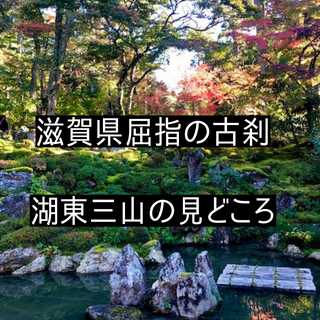
こんにちは!関西観光ガイドのyoshikiです🌏
近江屈指の古刹(こさつ)『湖東三山(ことうさんざん)』の魅力について、わかりやすく解説していきます。
11月の下旬にかけては様々なモミジやカエデが咲き乱れる「紅葉の名所」としても有名ですから、ぜひ最後まで読んでみて下さいね。
近江最古級の仏教寺院『百済寺』

寺伝によれば、今から1400年以上前の飛鳥時代。
聖徳太子によって創建されたという近江最古級の仏教寺院『釈迦山 百済寺(ひゃくさいじ)』
名称からもわかるように朝鮮半島の百済(くだら)国にあった「龍雲寺」をモチーフに創られた寺院だそうです。
実際、仏教をはじめとする建築技術を日本に伝えたのは百済系の渡来人と言われており
当寺の伝承からも百済と日本が良好な関係を築いていたことが伺えるのではないでしょうか?

本尊は
●十一面(じゅういちめん)観音菩薩
その名の通り、十一の顔を持つ変化身で
四方から十方まですべての人々を見守ってくれる観音菩薩です。
百済寺の由緒では、八日市の太郎坊山にあった聖木の下半分(根の付いた大樹)を使って彫られたことから「植木観音」とも称されています。
ちなみに上半分の幹で彫られたのは、百済の龍雲寺に安置された十一面観音だと言われ
「同木二体の観音様」として崇敬を集めました。
本尊は天台宗の総本山である「比叡山延暦寺(えんりゃくじ)」の根本中堂(本堂)と同様に秘仏であり、普段はその姿を拝見することはできません。

平安時代から中世にかけては1,000近くの僧坊を誇っており
宣教師ルイス・フロイスが祖国へ送った手紙には「地上の楽園 一千坊」と記したほど、それはそれは美しい光景だったようです。
しかし、戦国時代になると織田信長に抵抗を続けた六角氏に肩入れしたことから
焼き打ちの対象となり、残念ながら一千坊は全焼してしまうのでした。
それでも、江戸時代以降には多くの支援を得て見事に復興。
現在でも「天下遠望の名園」と称され、多くの人々を魅了しています。

11月下旬にかけて、カエデやオタフクナンテンが色付く滋賀県屈指の紅葉の名所としても知られていますから
参拝された際は、ぜひ美しい景観を一緒に楽しんでみて下さいね。
血染めのモミジで有名な『金剛輪寺』

奈良の大仏造立の立役者である大僧正"行基(ぎょうき)"によって開山されたと伝わる『松峯山 金剛輪寺』
●聖観世音(しょうかんぜおん)菩薩
十一面観音や千手観音のような変化身ではなく、一面二臂の人に近い姿形をした観音のことを指します。
とりわけ金剛輪寺の聖観音は「まだ未完成品ではないか?」と疑いたくなるほど、荒々しく彫られているそうですよ。
なぜ未完成な容姿をしているの?
その理由は行基に関する寺伝が関係しているんだよ
木肌から一筋の血が流れ落ちたため、その瞬間に魂が宿ったとして粗彫りのまま祀ったという伝承。
上記の寺伝から現在でも「生身の観音」と称され、篤い崇敬を集めています。

また、金剛輪寺の本堂には日本最古の大黒天が安置されていることでも有名ですね。
七福神の一柱である大黒天といえば、ふくよかな体型にニコやかな顔。
大きな袋を背負い、打出の小槌を持った姿を想像される方が多いのではないでしょうか?
しかし、天台宗の開祖である"最澄(さいちょう)"が唐から請来(しょうらい)した日本最古の大黒天はまるで別人!
不動明王のような憤怒(ふんぬ)の相をしているのです。
なぜ、金剛輪寺の大黒天は恐ろしい表情なのでしょうか?
その理由は、ヒンドゥー教の創造神シヴァの化身"マハーカーラ"を仏教に取り入れたものが大黒天だったからです。
マハーカーラ(シヴァ)は破壊と再生を司る闘神であり、時に死を意味する畏怖(いふ)の対象でもありました。
新たなモノが生み出されれば、同時に古いモノは淘汰されていく。
資本主義における"創造的破壊"の概念が、古来のインドから存在したというのは感慨深いものがありますね。
後に様々な神様と習合した結果
現在でこそ七福神のにこやかなイメージが定着している大黒天ですが、その始まりは恐ろしい神様だった。
そんな歴史の一端を学べるのも金剛輪寺の魅力の一つかもしれません。

11月中旬から下旬にかけて、モミジが美しく色付く紅葉の名所です。
とりわけ本堂から拝見できるヤマモミジやトウカエデは真っ赤に染まり
生身観音の伝承に因んで「血染めのモミジ」と称される人気のビューポイント!
本堂から三重塔まで向かう参道には、空がハートマークに見える知る人ぞ知る映えスポットもあります。

ハートマークの映えスポットは、本堂の職員さんが詳しく教えてくれるので
金剛輪寺を参拝された際は、せひ写真に納めてみてはいかがでしょうか。
鎌倉時代の純和様建築『西明寺』

平安時代初期に真言宗の僧"三修(さんしゅう)上人"によって開山されたと伝わる『西明寺(さいみょうじ)』
三修上人は、滋賀県最高峰の神名備「伊吹山(いぶきやま)」に弥高寺(現在は跡地のみ)を開山したことでも知られる伝説的な行者。
天台宗の寺院となった鎌倉〜室町時代にかけても祈願・修行道場として
約300の僧坊を有する寺院だったそうです。

織田信長の延暦寺焼き打ちの直後、比叡山傘下である当寺も焼き打ちの被害を受けたが
山門周辺を激しく燃やして全焼に見せかけたため、本堂・三重塔・二天門は火難を免れました。
そのため、初期飛騨の匠が建立(こんりゅう)した釘を使用しない鎌倉時代の純和様建築(本堂・三重塔)が当時のまま保存されています。

ご本尊は
●薬師如来
古来より医薬の仏として崇敬を集めており、比叡山延暦寺「根本中堂」の本尊(薬師如来)とは向かい合う形で祀られています。
延暦寺と同様に秘仏のため、普段はその姿を拝見することはできません。
ちなみに本堂の薬師如来像前にある西柱と南柱には、4尊の柱絵(菩薩)が描かれていたことが判明。
柱絵は飛鳥時代のもので、日本最古級の仏教絵画。
同時に西明寺の創建が平安時代以前である可能性を示す貴重な資材となっています。

西明寺の堺内には天然記念物の自然も豊富にあり
●1000本を超えるモミジ
●11月に満開を迎える「不断桜」
●樹齢約1000年の夫婦杉や龍の神木
●参道を彩る鮮やかな苔
を楽しむこともできます。
ぜひ近江屈指の古刹で、貴重な建造物と豊かな自然を堪能してみてはいかがでしょうか。